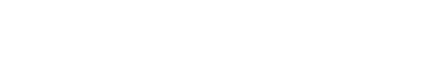1.サル類を用いた化学発癌実験とその腫瘍
高山昭三 (昭和大学) (座長 吉川泰弘)
2.Bウイルスの病理
柳井徳磨 (岐阜大学農学部),M. Simon(NERPRC)(座長 宮嶌宏彰)
3.Bウイルスの検査
藤本浩二(社団法人予防衛生協会) (座長 宮嶌宏彰)
4.類人猿の臨床(コンゴにおけるゴリラ・ボノボ孤児院も含め)
鵜殿俊史(三和化学研究所熊本霊長類パーク)(座長 後藤俊二)
5.サル類における鉤頭虫症
宇根有美1、岡林佐知1、堀 浩2、佐藤 宏3、野村靖夫1(1麻布大学獣医学部病理学研究室、2麻布大非常勤講師、3弘前大学医学部寄生虫学研究室) (座長 小野文子)
6.症例報告
1.チンパンジーのエルシニア症
江見美子 ((株)三和化学研究所 熊本霊長類パーク) (座長 前田博)
2.ニホンザルに認められたクマ蛔虫を疑う幼虫移行症
岸夏樹1、落合知枝子1、宇根有美1、佐藤宏2、野村靖夫1 1麻布大・病理、2弘前大・医・寄生虫 (座長 前田博)
1.サル類を用いた化学発癌実験とその腫瘍
高山昭三 (昭和大学) (座長 吉川泰弘)
- アメリカ国立癌研究所(NCI)で1961年から34年間遂行されたnonhuman primatesの研究について大略を報告する。
- NCIで行われたnonhuman primatesの飼育全般,定期検査,記録,剖検と組織検査について述べる。
- 34年間に381頭のnonhuman primatesが,いわゆるcontrolとして使用された。381頭に発生した自然発生良性・悪性腫瘍とその特色について報告したい。
- NCIでnonhuman primatesに長期間(20?32年間)投与した・癌化学療法剤,・食品中に作られた化学物質,食品添加物,・げっ歯類の発癌物質及び・ニトロソ化合物により形成された腫瘍と組織型について述べる。
2.Bウイルスの病理
柳井徳磨 (岐阜大学農学部),M. Simon(NERPRC)(座長 宮嶌宏彰)
近年,医学生物学の分野ではマカク属の需要が高まりつつある。マカク属サルを用いて実験を行うにあたり,一番問題になるのが人獣共通伝染病のBウイルス感染である。
Bウイルスの自然宿主はアカゲザルなどマカク属のサル類である。伝播は,サル同士では,接触,エアーゾル,人には噛み付き,引っかき,細胞培養により感染する。捕獲サルの70から100%が血清陽性で,症状が無くともウイルスを排出する可能性がある。病変はサル類とヒトでは質的には同様である。ヒトでは,Bウイルス感染時,暴露部位で水泡,潰瘍,強い痛みと痒み,痺れ,知覚異常などがみられ,最終的には全身リンパの腫大,発熱,筋肉脱力,麻痺,結膜炎が起こる。
臨床的には,口腔の水泡と潰瘍形成,結膜炎,稀に播種性感染がみられる。水泡にはウイルスが含まれる。口腔粘膜の潰瘍,出血を示します。サルでは,上皮細胞の風船様変性,多核細胞化,壊死がみられ,人では多中心性の壊死性脳脊髄炎,脾臓,肝臓,リンパ節,副腎の壊死が特徴である。
血清学的にBウイルス陽性とされたサルを解剖する場合の留意点につき示す。解剖には使い捨ての解剖着,前垂れを着用する。
- 必ずマスク,プラスチックのフェイスカバー,帽子,靴カバーを着用すること。
- 骨カッターは防塵装置付きの物を使用する。
- 傷口の手当てキットを準備する。
- 理想的には,個人用の空気ボンベを使用する。P3レベルの施設が望ましい。剖検者は,感染 を証明するためプレ血清をあらかじめ採取し保管しておく必要がある。
"マカクは全てウイルスを排出している"との前提にたって,サルの材料を処理することが必要。
全身に播種性感染を示した雌の1例を供覧する。症例は自家繁殖の4歳の雌で,難産後死産胎児を帝王切開で取り出した。腹膜炎を併発したため安楽死した。組織学的には,壊死巣が多臓器に認められ,しばしば多核細胞形成,封入体を伴っていた。免疫染色では,ヒトヘルペス1型と交差し,封入体に一致して,陽性像が認められた。
暴露された場合,その後2,3分が重要で,すぐ洗浄し,サンプル採取,次いで医師の診断を受けることが肝要。治療は,抗ウイルス薬のアシクロビルなどが有効。
3.Bウイルスの検査
藤本浩二(社団法人予防衛生協会) (座長 宮嶌宏彰)
Bウイルスの検査ではウイルス分離検査と抗体検査が行われる。
Bウイルス検査で重要な点はバイオハザード対策とBウイルスとヒトおよびサル由来αヘルペスウイルスとの判別である。
【ウイルス分離検査】
1999年4月に国立感染症研究所の病原体等安全管理規定が改訂され、診断を目的としたBウイルスの少量培養はバイオセーフテイレベル3で可能となり、培養細胞株等を用いた分離検査が行われる。
ウイルス同定と迅速診断を目的としてBウイルスのPCR検査法が開発され、PCR産物の制限酵素処理断片の比較(RFLP)や塩基配列の決定により、Bウイルスとヒトおよびサル由来αヘルペスウイルス5種がそれぞれ判別できる。
【抗体検査】
Bウイルス中和試験はバイオセーフテイレベル4での実施が必要であるため国内では行われていない。抗体検査は米国BioReliance社から輸入した不活化Bウイルス抗原を用いてELISA法で実施している。 Bウイルス抗体検査では抗体価の変動を考慮して定期的な実施が重要である。
ウエスタンブロット検査は確認検査として有用であるが、 抗原の調整や判定の基準など課題が残る。
ヒト血清中のBウイルス抗体検査では、単純ヘルペスウイルス抗体がBウイルスと反応するため、ヒト血清を単純ヘルペスウイルス抗原で吸収後検査をする必要がある。
Bウイルスの大量培養、抗原の調整はバイオセーフテイレベル4で実施する必要があるため、代替抗原として、Bウイルス由来のリコンビナント蛋白、アフリカ産サル由来αヘルペスウイルスの使用が検討されている。
【SPFサルコロニー】
Bウイルス抗体陽性の親ザルから仔ザルを早期に離乳する方法で未感染ザルが得られるため、これを第1世代SPF繁殖群としてコロニーを継代している。 SPFコロニーついては、定期的なBウイルス抗体検査を行い、感染の有無を確認することが重要である。
ワークショップでは、予防衛生協会で実施している検査の実際について説明したい。
4.類人猿の臨床(コンゴにおけるゴリラ・ボノボ孤児院も含め)
鵜殿俊史(三和化学研究所熊本霊長類パーク)(座長 後藤俊二)
類人猿科(Pongidae)に属するゴリラ、オランウータン、チンパンジーおよびボノボは大型類人猿とも呼ばれヒトに最も近縁なサル類である。いずれも絶滅の危機に瀕している。 このことは、同時に以下のようなこれら類人猿獣医療の特殊性をもたらす原因ともなっている。
- ヒトに非常に近縁であるため、多くのヒト用検査薬や医療器具がそのまま利用できる。生理学的にはほとんどヒトと同じで、膨大な人医学の情報や技術を利用することが出来る。しかし反面、ヒトの感染症のほとんどに感受性を持ち、飼育下では常にヒト由来感染症の危険にさらされている。
- ヒトに次ぐほど高度な知能を持つため、管理者の表情から意図を読みとり、混餌投薬を見抜くなど治療に抵抗するため、診療には工夫と熟練が必要で、時にはインフォームドコンセントも必要となる。
- 個性を持ち、個体ごとの性格や経歴を熟知しなければ個体の健康状態を把握することが出来ない。また、高い精神性を持つ為に、疾病時にはメンタルケアも必要である。
- 体が大きく力が強いため、診療の際には触診・聴診・採血さえ全身麻酔を必要とする。
- 飼育個体数は少なく、獣医学的基礎データや診療経験の蓄積が困難である。しかし40年以上ともいわれる寿命を幸福に全うさせるためには、高度な獣医療が要求されるだけでなく、種に特有な習性を理解し、飼育管理者とともに生活の質(QOL)を保証するための専門的知識が必要である。
このように類人猿の臨床には高度な専門性が要求されるが、国内には類人猿を専門とする獣医師はわずか3名おらず、手探りでの診療が続けられている。
発表では、三和化学で見られたチンパンジーの症例と診療経験を中心に、コンゴ共和国ゴリラ孤児院で見られたゴリラ、ボノボの症例を合わせて紹介し、類人猿の獣医臨床の現状を紹介する。
5.サル類における鉤頭虫症
宇根有美1、岡林佐知1、堀 浩2、佐藤 宏3、野村靖夫1(1麻布大学獣医学部病理学研究室、2麻布大非常勤講師、3弘前大学医学部寄生虫学研究室) (座長 小野文子)
鉤頭虫 Acanthocephala は、昆虫などを中間宿主として、主として小腸に寄生する蠕虫の1種で、条虫と線虫の中間形を呈しているといわれている。鉤頭虫門に属する蠕虫は、日本では、南西諸島のイノシシやブタにおける大鉤頭虫Macracanthorhynchus hirudinaceusとネズミなどの鎖状鉤頭虫Moniliformis spp.の存在が知られている。この2つの鉤頭虫は、ときにヒトにも感染するため、人畜共通感染症として捉えられている。今回、紹介するサル類に認められた鉤頭虫症は、南米のサルに良くみられるProsthenorchis属鉤頭虫で、海外の新世界ザル飼育施設で大きな問題を引き起こすことが知られている。国内では、輸入直後のサルの糞便検査で寄生を確認した報告はあるが、発症例あるいは集団発生の報告は見当たらない。今回、この鉤頭虫により高度に汚染された国内サル飼育施設で致死例の発生を見たので報告する。
【材料と方法】
約70種のサルを飼育する施設で、食欲不振、削痩、衰弱などにより、リスザル42頭中5頭が斃死した。この施設は3エリアより成り、死亡例はAエリアのみで発生し、うち4頭を病理組織学的に検索した。さらに同施設内のサル14種類(アカテタマリン、ムネアカタマリン、ワタボウシタマリン、クロクビタマリン、ドウグロタマリン、ワウワウテナガザル、シロガオオマキザル、ノドジロオマキザル、フサオマキザル、ヨザル、コモンマーモセット、コモンリスザル、ボリビアリスザル、ダスキーテイテイー)45頭の糞便と中間宿主のゴキブリを寄生虫学的に検索した。なお、同時期に他の疾患で死亡した5種のサル(ドウグロタマリン、コモンマーモセット、ピグミーマーモセット、アカテタマリン、ムネアカタマリン)も剖検した。
【結果】
病理学的所見:リスザル5頭(ボリビアリスザル3、コモンリスザル2)の回腸末端?盲結腸部を中心に、小豆大から小指頭大結節が見られた。管腔内には最大35.5mm長の様々な成長期にある鉤頭虫が認められ、ときに100余隻の虫体が内腔を閉塞していた。虫体は腸粘膜に深く侵入し、高度な例では、筋層にまで達し、貫壁性に肉芽組織によって置換され、壁がび漫性あるいは限局性に肥厚していた。また、膿瘍形成や腹膜炎を伴っていた。リスザル以外のサルでは、消化管内に虫体を認めたものの結節形成は見られなかった。寄生虫学的検査:今回の鉤頭虫症の原因はP. elegansと同定された。Aエリアの3種の新世界ザル(コモンリスザル、ドウグロタマリン、アカテタマリン)及びテナガザル計35頭の糞便検査で15頭に虫卵を確認した。虫卵は黄褐色、平均長径68.06×短径44.47μで、厚い卵殻を有していた。また、被嚢幼鉤頭虫(cystacanth)感染はAエリアのチャバネゴキブリ(Blattella germanica)のみで52匹中25匹と非常に高率に、成虫だけでなく幼虫からも検出された。また、ゴキブリ1匹あたりの寄生数は1?14で、体長2.29±0.30×0.53±0.02mm (n=7)であった。
【まとめ】
Prosthenorchis属鉤頭虫は、中南米産のサルに高率にみられる、高病原性の腸内蠕虫で、ゴキブリなどの中間宿主により感染し、効果的な治療法が確立されていない重要な蠕虫症とされている。このため、この種のサルを飼育する海外の施設では、この疾患のコントロールに十分注意を払っているようである。
日本では、近年、新世界ザルが展示用あるいはペットとして多数輸入されているにもかかわらず、これらを固有宿主とするProsthenorchis属鉤頭虫症に対する関心は低い。我が国では、過去に、今回のような集団発生の報告はなかったが、中間宿主であるゴキブリ対策が実施されていない場合には、国内でも生活環が完結し、さらに中間宿主の反復摂食によって感染が増幅し、濃厚感染個体では致命的となることがわかった。
人畜共通感染症としての鉤頭虫症の報告は、日本では、ゴキブリを食してしまったであろう1歳2ヶ月の大阪在住の男児にネズミの鉤頭虫であるMoniliformis dubius 感染が、また、中国では、中間宿主である甲虫を食べた子供でブタを終宿主とするM. hirudinaceus の数百例の重症患者の発生がある。Prosthenorchis属鉤頭虫に関してはヒトへの感染の報告はない。しかし、今回の検索で、新世界ザルに限らず、テナガザルにも感染が認められたことから、相当広い宿主域を有するものと推察された。このことから、飼育者・獣医師は十分に警戒しなければならない疾患である。
6.症例報告
1.チンパンジーのエルシニア症
江見美子 ((株)三和化学研究所 熊本霊長類パーク) (座長 前田博)
Yersinia pseudotuberculosis(以下仮性結核菌)は、ヒトを含む霊長類に急性経過をたどる致死的腸炎や敗血症を引き起こす人獣共通感染症起因菌のひとつである。低温でも発育するため、冬季に流行する特徴を持つ。
三和化学で群飼育されるチンパンジーにおいて、2年連続して冬季に仮性結核菌感染症が発生したので報告する。
2000年から2001年にかけての冬季に3頭で発生がみられた。発症した3頭は、約10日間の軟便?軽度下痢の後急速に悪化し、食欲不振?廃絶、赤褐色の軟便?下痢、ふらつき、衰弱が見られ、その当日から翌日に2頭が死亡した。1頭は治療により回復した。死亡した個体は三和産の11歳(♀)と9歳(♂)で、約150m離れた別の施設でそれぞれ飼育されている個体だった。回復した1頭は死亡した11歳(♀)と放飼場を共有する野生由来の19歳(♀)で、白血球数35、000(/mm3)と高値で、臍部に拳頭大腫瘤が触知され、低K血症を併発していたが、約20日間の抗生物質(CPZ)投与で治癒した。
死亡した2頭の病理学的検査では、小腸および大腸粘膜の広範な壊死、肝臓・脾臓の多中心性巣状壊死(米粒?大豆大の白色結節)、化膿性壊死性腸管膜リンパ節炎が見られ、壊死性腸炎と敗血症像を呈していた。糞便あるいは肝臓から仮性結核菌が分離されたが、2頭の菌株の血清型は3型および6型と異なり、複数の仮性結核菌の汚染経路があることが判明した。 PCR法による全頭の糞便中仮性結核菌DNA(vir-Fおよびinv)の定期的スクリーニングを導入したところ、2002年1月に2度(3頭)の発生が確認され、2頭では下痢、元気・食欲の低下が見られたが、1頭では無症状だった。いずれも2歳、6歳の若齢だった。3頭とも抗生物質(OFLX)の投与により2?4日で陰性化した。PCRでのスクリーニングを実施することで、仮性結核菌感染症の早期発見・治療が可能となった。同時に同居個体への予防的投薬と施設消毒を行い感染の拡大を防ぐことが出来た。
しかし、仮性結核菌の感染経路は未だ不明である。周辺で目撃される野生動物(ノネズミ、タヌキ、野鳥等)の糞便から仮性結核菌は今のところ検出されていない。現在飼料や水などを含めチンパンジーとの接触があると思われるものを幅広く検査し、原因究明を行っているところである。
2.ニホンザルに認められたクマ蛔虫を疑う幼虫移行症
岸夏樹1、落合知枝子1、宇根有美1、佐藤宏2、野村靖夫1 1麻布大・病理、2弘前大・医・寄生虫
(座長 前田博)
Baylisascaris属蛔虫による幼虫移行症はアライグマ蛔虫に代表される致死的な神経症状を引き起こす人獣共通感染症として問題となっている。今回、ニホンザルの1集団に神経症状を伴った幼虫移行症の発生をみたので報告する。
【経過】
ニホンザル(以下サル)約30頭とアメリカクロクマ、ツキノワグマを混飼している施設で、1989年より、てんかん、後躯麻痺などを呈するサルがみられるようになり、2001年2月まで断続的に、表1のように8頭が1日?12ヶ月の経過で斃死した。この施設では、サル・クマ飼育場はアライグマ飼育場に隣接しており、その排水は側溝に流入し、サルは自由に側溝に出入りしていた。なお、アライグマとクマには定期的に駆虫を行っており、クマにのみ蛔虫(Baylisascaris transfuga)の寄生が確認されている。
表1| No. | 年齢 | 経過(発症?死亡) | 臨床症状 | 脳病変の有無 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 4歳 | 1993.6.9?7.26 | (1.5カ月) | てんかん 有り |
| No.2 | 6歳 | 1996.1.20?7.4 | (6カ月) | 後肢麻痺、痙攣 ND |
| No.3 | 2歳 | 1998.7.4?9.9 | (2カ月) | 痙攣 有り |
| No.4 | 5歳 | 2000.6.17?2001.2.10 | (8カ月) | 後肢麻痺、痙攣 有り |
| No.5 | 2歳 | 2000.2.26?2001.3.5 | (1年) | てんかん 有り |
| No.6 | 1歳 | 1989.10.7?10.8 | (1日) | てんかん ND |
| No.7 | 1歳 | 1991.3.2?4.16 | (1.5カ月) | 後肢麻痺 ND |
| No.8 | 1歳 | 1991.3.28?7.4 | (3カ月) | 痙攣 ND |
(ND:未検査)
【材料と方法】
斃死したサル8頭中5頭(No.1?5)を病理学的に検索した。また、飼育施設内の土壌の虫卵汚染調査も行った。
【結果】
脳を検査した4頭全てに多発性脳軟化巣が観察された。軟化巣には、出血、格子細胞浸潤、肥満星状膠細胞の増数と浸潤、線維性グリオーシス、空洞化、好酸球、好中球やリンパ球浸潤が様々な程度と組み合わせで認められ、同一個体に新旧の軟化巣が観察された例もあった。病変は主として大脳に観察されたが、分布に一定の傾向はなかった。2頭のサルの脳(No.4)、肺(No.4,5)および腸間膜(No.4)に幼虫が認められた。幼虫は切片上で横径約60μmで、一対の側翼、左右対称性に排泄管を有し、回収した幼虫は体幅約80μm、尾部は鈍であった。また、土壌虫卵調査の結果、アライグマ飼育施設の土壌には虫卵は検出されず、サル・クマ飼育施設8カ所のうち、サル山の1カ所の土壌から直径65μmの蛔虫卵が回収された。
【まとめ】
以上の結果から、脳に蛔虫が確認されたのは1頭のみであったが、病理学的に検査した全ての脳に虫道形成と目される新旧の出血、軟化巣が認められ、詳細に観察できた症例において、大脳、肺、腸間膜に被嚢幼虫が観察されたこと。その被嚢幼虫の形態はBaylisascaris属蛔虫の形態と一致したことより、これらのサルはBaylisascaris属蛔虫による幼虫移行により神経症状を呈し、死に至ったものと推察された。Baylisascaris属蛔虫には、いくつかの種類があるが、疫学調査の結果と幼虫の形態から、今回の集団発生の原因としてアライグマ蛔虫あるいはクマ蛔虫が考えられた。この2種の幼虫形態は酷似し区別は難しいが、現在のところ尾部の形態によってのみ鑑別可能とされており、肺から分離された幼虫の尾部の鈎状突起はクマ蛔虫のそれと類似していた。この施設では、アライグマにかつて蛔虫の寄生が確認されたことがないことからクマ蛔虫による幼虫移行症の可能性が高いと考えた。クマ蛔虫においても幼虫移行症が起こることが、実験的に証明されているが、ヒトを含めて動物には自然発生性幼虫移行症の報告はなく、本症例は、ニホンザルにおけるクマ蛔虫を疑うBaylisascaris属蛔虫幼虫移行症の初めて報告である。Baylisascaris属蛔虫卵は2?4週間あるいはそれ以上かけて感染力を有し、土壌中で何年も感染力を持ち続ける。これらの蛔虫卵で汚染された土壌との接触がBaylisascaris属蛔虫感染のもっとも重要な危険因子であり、汚染土壌における清浄化の徹底が望まれる。